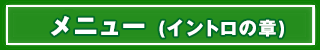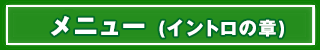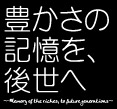

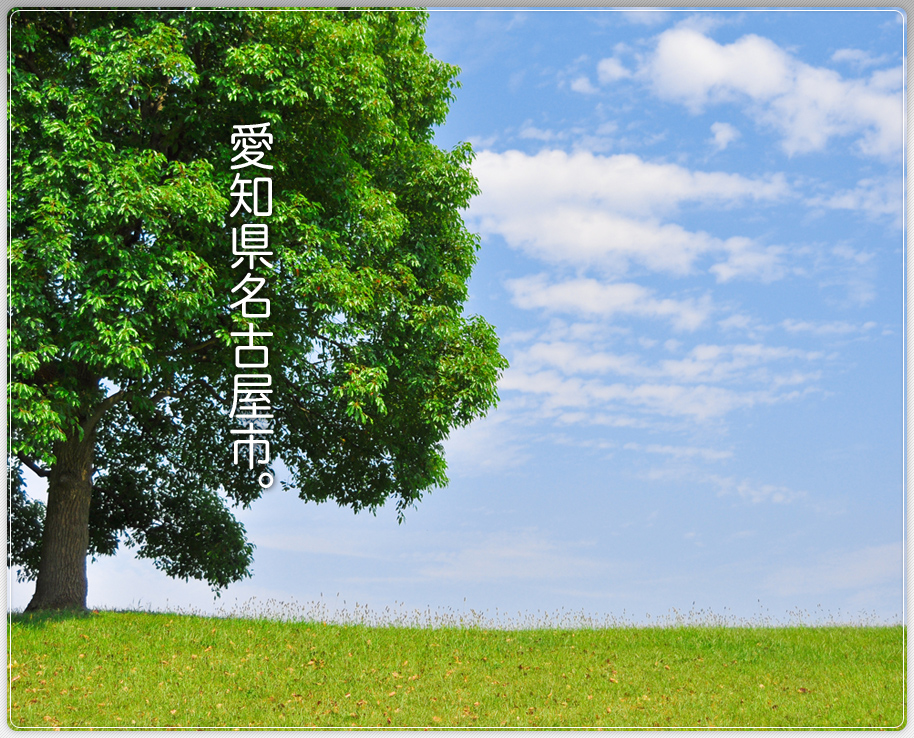
加藤徹の自宅のすぐそばに、広い空き地があった。
ぽつんと一本くぬぎの木が立つ、都会にしては珍しい昔ながらの原っぱ。そこは実は、とある民間会社の私有地ではあったのだが、特に厳しい立ち入り制限があるわけでもなかった。そこで遊ぶ近所の子供たちの嬌声が、よく聞こえてきた。
加藤自身も、休みの日には3人の子供たちを誘い、その原っぱで野球をしたり、一緒に走り回ったりして遊んだ。
ある春の休日のこと。加藤はいつものように子供たちと共に、その原っぱに出向いた。
『見て見て!ダンゴムシ!』
末っ子の次女が小さな手で大切そうに包み込んで加藤に見せてくれたのは、身体を丸めたダンゴムシ。 二人で様子を窺っていると、ダンゴムシはやがて身体を伸ばし、怪訝そうに触覚を動かしながら、とことこと歩き出す。
その手のひらのこそばゆさに、幼い娘は無邪気に笑った。
ぽつんと一本くぬぎの木が立つ、都会にしては珍しい昔ながらの原っぱ。そこは実は、とある民間会社の私有地ではあったのだが、特に厳しい立ち入り制限があるわけでもなかった。そこで遊ぶ近所の子供たちの嬌声が、よく聞こえてきた。
加藤自身も、休みの日には3人の子供たちを誘い、その原っぱで野球をしたり、一緒に走り回ったりして遊んだ。
ある春の休日のこと。加藤はいつものように子供たちと共に、その原っぱに出向いた。
『見て見て!ダンゴムシ!』
末っ子の次女が小さな手で大切そうに包み込んで加藤に見せてくれたのは、身体を丸めたダンゴムシ。 二人で様子を窺っていると、ダンゴムシはやがて身体を伸ばし、怪訝そうに触覚を動かしながら、とことこと歩き出す。
その手のひらのこそばゆさに、幼い娘は無邪気に笑った。

秋にくぬぎの木から落ちたどんぐりが芽を出し、つくしやタンポポが他の雑草に負けじと生い茂る。
草むらに隠れていた小さな虫たちが、
春の日差しを求めて動き出す。
加藤は子ども達と共に雑草をかき分け、飽きることなく新たな『いのち』探しに夢中になった。
自分が子供だった頃を思い出し、捕まえた虫のウンチクをたれてみたり、逆に図鑑で予想外に博識になった子どもたちに、ダンゴムシの性別の見分け方を教えられたり。
様々な『いのち』が輝く、都会の中の小さな自然。
ささやかながらも、心が豊かになるひととき。
自分が子どもの頃には、比較的都心に近いところでも、原っぱや田んぼが広がっていた。 春には花を摘み、夏には虫やザリガニを捕え、秋には木の実を採り、冬には凍えながらも雪で遊んだものだった。
草むらに隠れていた小さな虫たちが、
春の日差しを求めて動き出す。
加藤は子ども達と共に雑草をかき分け、飽きることなく新たな『いのち』探しに夢中になった。
自分が子供だった頃を思い出し、捕まえた虫のウンチクをたれてみたり、逆に図鑑で予想外に博識になった子どもたちに、ダンゴムシの性別の見分け方を教えられたり。
様々な『いのち』が輝く、都会の中の小さな自然。
ささやかながらも、心が豊かになるひととき。
自分が子どもの頃には、比較的都心に近いところでも、原っぱや田んぼが広がっていた。 春には花を摘み、夏には虫やザリガニを捕え、秋には木の実を採り、冬には凍えながらも雪で遊んだものだった。

・・・そう言ったのは、ルソーだったか?
確かに自分も、自然の中で遊びながら学んだ事がたくさんあると思い当たった。自然の中で様々な生物と接し、季節の移り変わりを感じた。自然の力に圧倒され、怖い思いもした。遊びを通して、世の理を教えてくれる自然。これほど豊かで、かつ贅沢な教材は、他には無いのではないかと思えてくる。
しかし、今はどうだろう?
あの頃に比べ物質的に恵まれ、便利な生活を送っている今の子ども達。
しかし彼らは、利便性を追及し創り上げられた無機質な『セカイ』の中で、本当の『豊かさ』を実感できているのだろうか?
もちろん、技術の進歩を否定する気は毛頭ない。技術のおかけで、世界の時間的距離は急激に縮まり、情報は好きな時に好きなだけ手に入る。
野菜や果実は絵に描いたように美しい造型をし、衛生的な環境に身を置き、病原菌から身を守ることが出来る。
自分が属する建設業界で言えば、
生活におけるインフラ整備は全国的に整備され、。狭い国土を活用するため、高層ビルや地下鉄なども造られた。
技術が進歩することで、人々はより便利に暮らすことができる。
確かに自分も、自然の中で遊びながら学んだ事がたくさんあると思い当たった。自然の中で様々な生物と接し、季節の移り変わりを感じた。自然の力に圧倒され、怖い思いもした。遊びを通して、世の理を教えてくれる自然。これほど豊かで、かつ贅沢な教材は、他には無いのではないかと思えてくる。
しかし、今はどうだろう?
あの頃に比べ物質的に恵まれ、便利な生活を送っている今の子ども達。
しかし彼らは、利便性を追及し創り上げられた無機質な『セカイ』の中で、本当の『豊かさ』を実感できているのだろうか?
もちろん、技術の進歩を否定する気は毛頭ない。技術のおかけで、世界の時間的距離は急激に縮まり、情報は好きな時に好きなだけ手に入る。
野菜や果実は絵に描いたように美しい造型をし、衛生的な環境に身を置き、病原菌から身を守ることが出来る。
自分が属する建設業界で言えば、
生活におけるインフラ整備は全国的に整備され、。狭い国土を活用するため、高層ビルや地下鉄なども造られた。
技術が進歩することで、人々はより便利に暮らすことができる。

・・・ただ、技術の進歩の中で、脈々と『いのち』が連鎖し循環する豊かな『自然』の姿を目の当たりにできる場所と機会は、極端に減ってしまったように思える。
残念なことに世間では、自分が誇りに思っている仕事・・・
建設業こそが、このさまざまな
『いのち』との共生を阻害する根源のように言われている。
しかし、決してそうではない。
むしろ、現在の便利な生活と、
懐かしく美しい自然との共生を提案し、実際に実現することができるのは、建設業なのではないだろうか。
失われつつある多様な『いのち』と共生できる場所を大切にする『美しいまち』を創り、その暮らしの中で育まれる『豊かさの記憶』を後世へ伝えて行くことができるのは、自分たち建設業なのではないだろうか。
大地を相手に仕事をし、自然の美しさと怖さを知る者として。
大地を大きく動かすことのできる、技術ある者として。
そして、失われつつある昔ながらの風景を知る、
地元の者として。
これまで自然災害から地域を守り、くらしを支えてきた建設業。 自分たちの建設に携わる者たちが、考え方を少し柔軟にし、
創りだすものを人の都合を優先したものだから、
自然の循環の中に溶け込むものへ工夫するだけで、
自然との共生は必ず実現できる。
そしてそれは、自分たち建設業が、再び地域から無くてはならない存在になることに、繋がっていくのではないのだろうか。
残念なことに世間では、自分が誇りに思っている仕事・・・
建設業こそが、このさまざまな
『いのち』との共生を阻害する根源のように言われている。
しかし、決してそうではない。
むしろ、現在の便利な生活と、
懐かしく美しい自然との共生を提案し、実際に実現することができるのは、建設業なのではないだろうか。
失われつつある多様な『いのち』と共生できる場所を大切にする『美しいまち』を創り、その暮らしの中で育まれる『豊かさの記憶』を後世へ伝えて行くことができるのは、自分たち建設業なのではないだろうか。
大地を相手に仕事をし、自然の美しさと怖さを知る者として。
大地を大きく動かすことのできる、技術ある者として。
そして、失われつつある昔ながらの風景を知る、
地元の者として。
これまで自然災害から地域を守り、くらしを支えてきた建設業。 自分たちの建設に携わる者たちが、考え方を少し柔軟にし、
創りだすものを人の都合を優先したものだから、
自然の循環の中に溶け込むものへ工夫するだけで、
自然との共生は必ず実現できる。
そしてそれは、自分たち建設業が、再び地域から無くてはならない存在になることに、繋がっていくのではないのだろうか。

『豊かさの記憶』を、後世へ。
それが今、自分たち建設業に携わる者たちが、
子ども達のために出来ること。