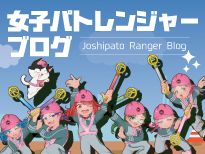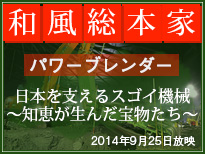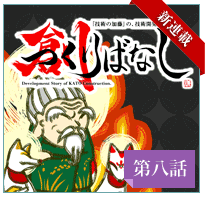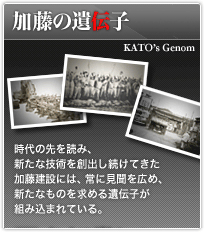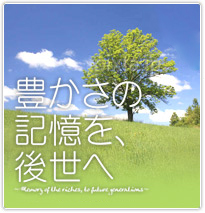エコミ―ティング(ビオトープ管理士)
テントウムシを探せ!なごや生きもの一斉調査に参加してきました!
みなさん、こんにちは!
今回は、名古屋市内を中心に野生生物の調査や保護、外来種対策などの保全活動を行っている
「なごビオ(なごや生物多様性保全活動協議会)」主催の
なごや生きもの一斉調査2021に参加した際の様子をご紹介します!!!
まず、なごや生きもの一斉調査とは?
市民と専門家が協力して、年に1度 名古屋市内の生きものを調査する活動です。
市民の方々に、身近な自然や生きものに親しみ、より関心をもってもらうことを目的としています。

調査する生きものは、毎年変わり、
今年のターゲットは“テントウムシ🐞”
ちなみに去年は “バッタ”でしたよ。
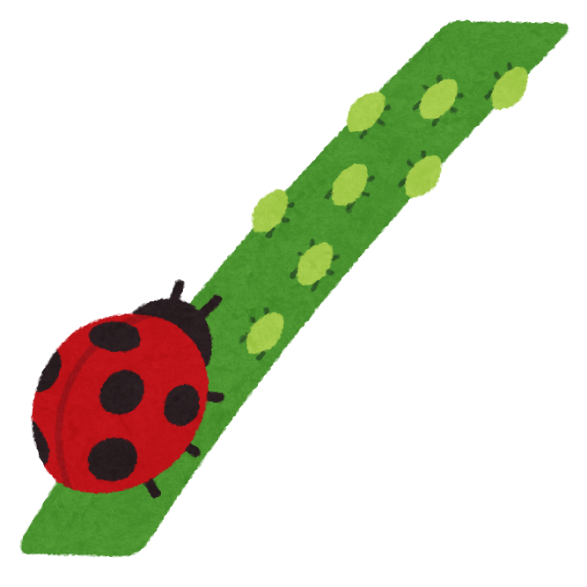
調査する場所は、名古屋市内の公園や緑地、約40地点!
その中から、1つを選んで調査を行います。
今回、私たちが調査したのは、
名古屋市港区の “荒子川公園”

キレイなお花や様々な種類の樹木が植えられた市民の憩いの場所です。
もちろん、草地もあるため、たくさんの昆虫がいることは間違いなし!
~それでは見ていきましょう!~
荒子川公園に到着して、
まず初めに、現地のリーダーとサブリーダーから
テントウムシがどのような場所に生息しているのか、
見つけるポイントなどのレクチャーを受けます。
しっかりとテントウムシについて理解したところで…
まずは、お花がキレイに咲く花壇を中心に捜索です。
テントウムシの大好物なアブラムシがついていそうな植物を丁寧に見て探します。


ちなみに、調査中はこのビブスを着用します!
なんだか本格的ですね♪


テントウムシとよく似た、ハムシの仲間やカメムシの仲間はいるのですが、
テントウムシは見つかりません…うーんどこにいるんだぁ~
今度は、樹木が植えられているエリアへ移動して探します。


テントウムシは、樹皮の裏などに密集して冬眠をする習性があるため、
樹木の周りを隈なく探していきます。


ここでようやくテントウムシを発見!
木の葉っぱの裏にとまっていました!
この子の名前は “シロホシテントウ”
白い水玉模様がとっても可愛いテントウムシです。
アブラムシではなく、
葉っぱの表面に白いカビは生える

「うどんこ病」などの“菌”を主食にしているようです。
変わってますね!
最後は、草地のエリアに移動して
“スウィーピング”という方法で、虫捕り網を使ってテントウムシの捕獲を試みます!
ちなみに、スウィーピングとは、
草をなでるように虫取り網を振り、葉や茎に付いている昆虫を掬いとる方法のことです。

その結果…
なんと!?たくさんのテントウムシが見つかりました!
全然見つからなくて、内心焦っていたので、見つかって本当に良かったです!
捕獲したテントウムシは、
チャック付の袋に入れて持ち帰ります。


持ち帰ったテントウムシは、
図鑑や資料を参考に“同定”を行います。


この同定作業はとても大変!
小さなテントウムシと資料を交互ににらめっこ!
なかなか種類が判別できません!!
それもそのはず、テントウムシは日本に201種類いると言われており、
名古屋市ではそのうち約50種類が確認されているとのことです。
こんなにも多くの種類がいるとは知りませんでした!
そしてようやく、種類を判別することが出来ました! それがコチラ↓↓↓

なんだか聞いたことがない種類ばかりですね!!
黒、白、赤など色んな色のテントウムシが見られました!

ちなみに、皆さんがテントウムシと聞いて一番に思い浮かべる
“ナナホシテントウ”は今回の調査では確認されませんでした。
テントウムシの仲間は、先ほど紹介した菌を食べる種類の他に
アブラムシなどの他の昆虫を食べる肉食の種類や植物を食べる草食の種類など
それぞれ食べ物に好みがあるようです。面白い!
“食べ物”や“姿形”や“色”や“大きさ”など
テントウムシがこれほどバリエーションに富んだ生き物であるとは、
調査をするまでは全然知りませんでした!!
テントウムシについて深く学ぶことが出来て、大変勉強になりました!
来年の一斉調査も是非参加したいと思います!
それでは~!